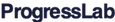ネガティブを成長に変える!主体性を引き出す承認質問の極意
「なぜですか?」の罠:主語を変えて主体的な行動を引き出す承認質問
こんにちは、坂本です。皆さんのキャリアと組織の成長を応援しています。
昨日の記事では、クレームというネガティブな場面を、いかに「感謝+A(アダルト)」のストロークで、信頼創造の機会に変えるかという実践的な対話術についてお話ししました。
さて、今日のテーマは、ビジネスの日常で最も多く、そして無意識に使ってしまいがちな「危険な一言」についてです。それは、「なぜ、あなたはこれをやらなかったのですか?」という「なぜ?」の質問です。
指導やフィードバックの場面で、私たちは良かれと思って「なぜ?」と問いかけます。しかし、この一言は、聞かれた相手の主体性を瞬時に奪い、心の中に「無条件の否定的ストローク」の壁を作ってしまう「罠」となりかねません。特に、若手社員や顧客への指導において、この罠は成長を阻む最大の障壁となります。
本記事では、この「なぜ?」の罠から脱却し、相手の行動変容と自己肯定感(I’m OK)を高めるための「承認質問」の技術を解説します。これは、ドラッカーが提唱した目標による管理(MBO)の思想にも深く通じる、プロの指導者が持つべき対話設計図です。
「なぜ?」が引き起こす、心のシャットダウン(否定的ストローク)
指導者が「なぜ?」と問う時、その真意は「原因を知り、改善したい」というポジティブな意図にあるはずです。しかし、この一言が相手の心には、しばしば「批判的な親(P)」からの「無条件の否定的ストローク」として届いてしまいます。
この章では、「なぜ?」のストロークが、相手の心理と行動に与える悪影響を、TA(交流分析)の視点から分析します。
主語が「あなた」になることの心理的負荷
「なぜ?」の質問は、文法上、主語が「あなた」、述語が「失敗・ミス」になります。
例:「なぜ(どうして)、あなたは、この重要な手続きを省略したのですか?」
この質問形式は、「あなたは手続きを省略した」という行動ではなく、「あなたという存在」そのものに責任を問うニュアンスを帯びてしまいます。問いかけられた側は、自分の存在(I’m OK)が危機に瀕したと感じ、心を守るために反射的に「防衛反応」を起こします。
- 防衛反応の例: 言い訳をする、他者のせいにする、沈黙する、フリーズする。
こうなると、対話の目的であった「原因究明と改善」は後回しにされ、指導者は「批判的な親(P)」、相手は「反抗的な子ども(C)」という非生産的な交流(非効率な交差交流)に陥ってしまうのです。
「なぜ?」の質問は「過去」に焦点を当ててしまう
ドラッカーは、知識労働者のマネジメントについて、常に「成果」と「未来」に焦点を当てることの重要性を説きました。しかし、「なぜ?」の質問は、問答無用で「過去の失敗」へと焦点を固定してしまいます。
過去に焦点を当てた議論は、「もしあの時こうしていれば…」という後悔や自責の念(否定的ストローク)を呼び起こすだけで、具体的な未来の行動変容には繋がりません。
プロの指導者が焦点を当てるべきは、「過去の失敗」ではなく、「未来の成功」です。失敗の原因は簡潔に把握し、その後の対話のエネルギーは全て「どうすれば、次回成功できるか?」という未来志向の問いに注ぎ込むべきなのです。
承認質問は「主語」を「行動」と「未来」に変える
この「なぜ?」の罠から抜け出すためのカギとなるのが、「承認質問」です。承認質問とは、「あなたの存在や頑張り」を前提として認め(承認ストローク)、「具体的な行動」と「未来」に焦点を当てた質問をすることです。
具体的には、「なぜ?」を「どうすれば?」や「次は何を?」に置き換えることで、質問の主語が「あなた」から「行動」へと変化します。
- NG(過去・存在): なぜ、あなたはあのミスをしたのですか?
- OK(未来・行動): このミスを教訓に、次はどの手順から見直すのが最も効果的だと思いますか?
これにより、相手は防衛的になることなく、「改善の責任」を自ら引き受ける主体性(I’m OK, You’re OKの精神)を発揮しやすくなります。
行動変容を促す「承認質問」の具体的な設計図
承認質問は、以下の3つの要素を組み合わせて意図的に設計されます。これは、顧客の「損失回避」の心理を「挑戦」へと反転させる、強力な対話技術です。
ステップ1:無条件の承認で心理的安全性を確保する
質問に入る前に、必ず無条件の肯定的ストロークで相手の存在を認め、心理的安全性を確保します。
実践例文:
状況: 新しいITツールの利用者が、何度注意しても重要なデータ保存プロセスを省略した。
ストローク: 「〇〇さん、今は少し落ち込んでますね。この新しいシステムに、真剣に向き合って使いこなそうとしていることはよく分かります。(無条件の承認)あなたがこの業務を円滑に進めたいと願う気持ちは、私も全力で応援しています。(無条件の承認)さあ、少し深呼吸しましょう。」
この「真剣に向き合っている」という努力や存在そのものを承認することが、相手を「反抗的な子ども(C)」から「協力的な大人(A)」へと変える、魔法のスイッチになります。
ステップ2:「どうすれば?」で主語を未来の行動に変える
心理的安全性が確保されたら、質問の主語を「あなた」から「行動」に変える「どうすれば?」の質問を投げかけます。これにより、相手の思考を「後悔」から「解決策の創造」へと強制的にシフトさせます。
実践例文:
状況: 担当した顧客のクレーム対応が遅れ、状況が悪化した。
NG(なぜ): 「なぜ、あなたはあの時にすぐに報告しなかったんだ?」
OK(どうすれば): 「今回、報告が遅れたことで、状況がどう変わったか教えてくれますか?この教訓を活かして、次回以降、『遅れる状況』になったら、私たちは何を最初にすべきだと思いますか?」
「教訓を活かして」という言葉は、相手の失敗を「学習」として位置づけるポジティブなストロークです。そして、「私たちは何を」と問いかけることで、個人の問題を組織全体の改善(A:アダルトな視点)へと昇華させます。
ステップ3:「強み」への焦点で挑戦意欲を高める
承認質問の最後は、相手が持つ潜在的な強みに焦点を当てて締めくくります。これにより、相手は「自分にはこの課題を克服できる能力がある」という確信(I’m OK)を得て、次の行動への動機づけが完了します。
実践例文:
状況: 新しい企画が途中で頓挫してしまった。
ストローク: 「〇〇さんの『途中で諦めない粘り強さ』は、誰もが知っていますよ。(強みの承認)この粘り強さを、次の企画のどの段階で、どのように活かしていきたいですか?」
「強み」に焦点を当てることで、相手は自分の存在価値を再認識し、「失敗した事実」ではなく「成功できる未来」に向けて自ら責任を負う決意を固めることができるのです。

CX指導への応用:利用者の「できない」を「できる」に変える対話
この「承認質問」の技術は、社内の指導だけでなく、顧客への指導(例えば新しいITツールの導入トレーナー)にもそのまま応用できます。顧客や利用者の「できない」というネガティブな感情を、「できる」というポジティブな行動に変えるのが、プロのCX設計です。
顧客の「Why Me?(なぜ私だけ?)」を解消する
新しいツールやシステムを導入した利用者がミスを繰り返すとき、「なぜ、私だけこんなにできないのだろう?」という「Why Me?」の心理状態に陥りやすいものです。これは、「無条件の否定的ストローク」を自らに与えている状態です。
トレーナーやコンサルタントは、この時こそ「承認質問」で対応します。
指導例:
トレーナー: 「〇〇さん、今、すごく悔しい気持ちになっているのが伝わってきます。(感情の承認)でも、悔しいと感じるのは、本気で上達したいと思っている証拠ですよ。(努力を承認)さて、このミスを防ぐために、『今』、あなたが最初に確認できる手順は、何だと思いますか?」
「あなたが最初に確認できる」と問うことで、責任を相手に戻し、「私にもできる」という主体的な解決を促します。
ドラッカーMBOの精神:「自己管理」を促す対話
ドラッカーの目標による管理(MBO)は、単なる評価制度ではなく、「部下が自らを管理し、成果を上げること」を促すための哲学です。指導者や上司の役割は、「部下の成果を決定し、それを達成するための支援を行うこと」です。
承認質問は、まさにこのMBOの精神を体現しています。
- 成果の明確化: 「次、どこまでできるようになることを目標にしますか?」
- 支援の提案: 「その目標達成のために、私からどのような情報を提供すれば、最も役立つでしょうか?」
このように問いかけることで、相手は「自分の目標は自分で決める」という自律性を発揮し、指導者との関係はP-C(親–子ども)ではなく、A-A(大人–大人)の協力関係へと進化するのです。
【まとめ】主体性を「創造」するプロの質問設計
今日の記事では、「なぜ?」の質問が持つ心理的な罠を理解し、主体的な行動変容と成長を促すための「承認質問」の設計図を解説しました。
- 意識の転換: 質問の焦点を「過去の失敗」から「未来の行動」へ変える。
- ストロークの設計: 無条件の承認で安心させ、「どうすれば?」で行動に責任を負わせる。
- 強みへの焦点: 失敗を責めず、その裏にある潜在的な強みを指摘し、次の挑戦への動機づけとする。
あなたの質問は、相手の心を閉ざす壁にも、未来へと開く扉にもなり得ます。プロとして、常に「相手の成長」という成果に焦点を当てた質問の創造に挑戦し続けてください。
お読みいただきありがとうございました。皆さんのキャリアと組織の成長にお役に立てれば幸いです。